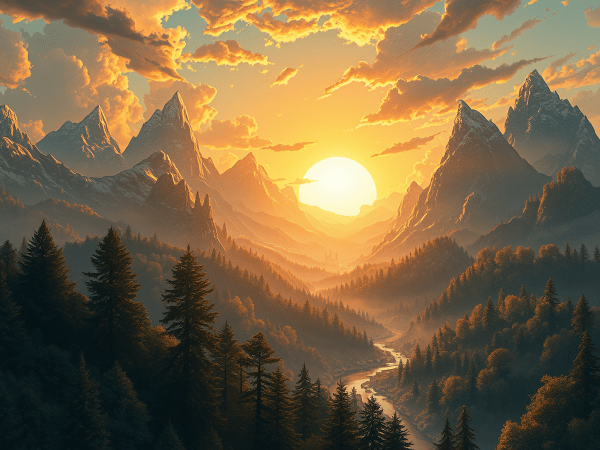「希望退職者を募集します」
最近、大手企業のニュースでこの言葉を目にしない日はありません。
2025年の調査では、早期・希望退職を募集している企業の約8割がプライム上場であり、対象人数は11045人にも上ります。
電機、銀行、製薬、IT……。業種は違えど、多くの企業が人手不足で黒字であるのにもかかわらず、「構造改革」や「次なる成長のため」という旗印を掲げ、社員に決断を迫っています。
会社側の説明は、いつも決まって前向きです。
- 「新しいキャリアへの挑戦を応援します」
- 「第二の人生を全力でサポートします」
- 「割増退職金で、あなたの次のステップにブーストを」
人事部の資料に並ぶのは、未来への希望に満ちた言葉ばかり。しかし、その裏側で起きている現実は、決してそんな綺麗なものではありません。
SNSのタイムラインを見れば、そこにはある共通のパターンが浮かび上がります。
「一番尊敬していた○○さんが辞めてしまった」
「あのエース級の先輩まで会社を去るなんて……」
そんな嘆きの声が、現場から次々と聞こえてくるのです。
一方で、周囲から「正直、この機会に……」と内心思われているような層に限って、意外なほど静かに、そしてしっかりと会社に残り続けています。
これは、単なる偶然ではありません。 実はこの制度には、多くの経営者が目を背けている、あるいは気づいていない”構造的な落とし穴”があるのです。そして面白いことに、これと全く同じ現象が、今から50年前のフランスでも起きていました。
舞台も状況も違う。けれど、起きたことは驚くほど似ている、、、いや、殆ど同じといってもいいかもしれません。
それは、1970年代のフランス政府が打ち出した、ある”人道的な”政策の物語です。
移民帰国推奨政策が招いた「皮肉な結末」
1970年代のフランスも今の日本企業とよく似た、いわば「逆選択の罠」に陥りました。
時は第二次世界大戦終結後まで遡ります。
終戦後のフランスは復興と成長の時代を迎え、その後のおよそ30年間は、栄光の30年間(Les Trente Glorieuses)と呼ばれる、空前絶後の経済成長期でした。
戦争で多くの働き手が失われたこともあり、この時フランス国内は急激な発展によって深刻な労働力不足に悩まされました。この問題を解決するため、フランスは海を越えて多くの移民を招き入れるようになります。
特に同じフランス語圏であり、かつてフランスの植民地だったアルジェリアやモロッコといった北アフリカの国々、そして比較的賃金の低かった南欧のポルトガルやスペイン等から、多くの移民が希望を胸にフランスへ渡っていきました。

INSEEの”L’essentiel sur… les immigrés et les étrangers “記事内のデータを基に筆者作成
彼ら移民は、目立たないながらも国の屋台骨を支える存在でした。建設現場で街を作り、自動車工場で製品を生み出し、まさにフランスのインフラと産業を駆動させていたのです。
しかし、この黄金期は永遠には続きませんでした。
1973年、中東戦争をきっかけとするオイルショックが世界を直撃すると、好景気は急速に冷え込み、フランス経済は深刻な不況に陥ります。街には失業者が溢れ、社会の雰囲気は一変しました。
そこで事態を打開するため1977年、当時の移民労働者環境庁長官であるリオネル・ストレル(Lionel Stoléru)は帰国推奨政策(million Stoléruとも呼ばれた)を導入します。
これは一定の条件を満たした外国人労働者が、フランスでの居住権と労働の権利を一切放棄して本国へ帰る場合、帰国用の無料航空券と一律1万フラン(現在の約100~150万円に相当)を与えるという思い切った策でした。
「これなら失業中でスキルの低い、特に北アフリカからの移民たちも喜んで国に帰ってくれるだろう。。。」それが政府の狙いでした。
しかし、この一律支給という安易な設計が、皮肉な結末を招きます。政府が意図したのとは真逆の人々が動いてしまう、逆選択の罠にはまったのです。
なぜ「優秀な層」だけが消えたのか
帰国推奨政策は、歴史に残る致命的なミスマッチを引き起こしました。
この制度は政府の意図とは裏腹に、最も”残ってほしい”と考えられていた、比較的帰国後の選択肢が多い南欧出身者が多く利用し、逆に”去ってほしい”とされていた、帰国後の生活が不安定な北アフリカ出身の移民等の利用は比較的少なかったのです。
この背景には、当時のフランスが抱えていた経済不況以上に深刻な社会統合への不安があります。
南欧移民は宗教や生活様式がフランス社会と比較的近く、いずれは母国へ帰る一時的労働者と見なされていました。
一方で、北アフリカからの移民は都市郊外(バンリュー)に集中居住し、イスラム文化の可視性も高かったため、政治や世論の中で同化しにくい存在として問題視されるようになっていったのです。
なぜこのような結果になったのか、、、そこには、人間が持つ市場価値と選択肢の有無に基づく、極めて合理的で冷徹なメカニズムが働いていました。
リスクを取れる「選択肢を持つ者」の決断
真っ先に手を挙げたのは、母国で経済成長が始まり、「帰国してもやっていける」という展望を持てた人々でした。
彼らにとって、支給された1万フラン(当時の最低賃金の約半年分)は、母国で家を建てたり、商売を始めたりするための計算可能な初期投資に過ぎません。
「ここ(フランス)以外でも生きていける」
その自信と選択肢があったからこそ、彼らは合理的にフランスを去る決断ができたのです。
動けない「依存せざるを得ない者」の停滞
一方で、母国の経済が不安定で、学歴・技能・言語の面でハンデを抱える層は動きませんでした。
正確に言えば、動かなかったのではなく、動けなかったが正しいでしょうか。
彼らにとっての1万フランは、フランスの社会保障(失業手当、医療、住宅補助)を捨ててまで賭けに出るには、あまりにもリスクが高すぎたのです。
さらに決定的だったのは、1970年代後半にはすでに移民2世の存在が現実のものとなっていたことです。
フランスで生まれ、フランス語を母語とし、学校も友人も生活基盤もフランスにある若者たちにとって、母国とはもはや帰る場所ではなく、殆ど縁のない外国でした。
「ここを離れたら生きていけない」
そう悟った彼らは、肩身の狭さを感じながらも、制度にしがみつくという選択を取らざるを得なかったのです。
事実、フランス政府の期待に反して、この帰国支援制度を利用した移民はそれほど多くはなく、特に最も同化が難しいと見なされていた北アフリカからの移民たちほど、この帰国推奨政策を利用する可能性が最も低かったんです。
現代の日本企業に潜む「同じ罠」

この構造は現在、日本で起きている希望退職制度に似ているのではないでしょうか?
企業の制度設計が意図した効果とは異なり、比較的“動きやすい人”が先に制度を利用しやすいという傾向です。
真っ先に手を挙げるのは誰か?
割増退職金という”おまけ”をもらって喜んで去っていくのは、外でも十分やっていける優秀なエンジニアや実績ある営業マンです。彼らは「この会社、もう先がないな」と見切りをつけ、退職金を軍資金に次のステージへと進んでいくのです。
最後まで居座るのは誰か?
一方で、会社に残るのは転職なんて無理だと不安を抱える人たちです。スキルに自信がなく、転職に不安を抱え、現在の職場にとどまらざるを得ない人たちほど、退職金の誘惑には乗らず、しっかり席を確保しつづけるのです。
まとめ
人件費という”コスト”は削れても、同時に失うのは現場で積み上げられてきた知恵や信頼、そして組織を前に進めてきた優秀な”人財“です。結果として、組織にはどこにも行けない”人在”が残りがちになり、再生はさらに困難になります。
希望退職制度では、外でも通用する選択肢を持つ人から先に動きます。一方で、不安を抱える人ほど会社に残ります。
結果として起きるのが、この皮肉です。
1970年代のフランスで、帰国奨励政策が意図せず”動ける人”から社会を去らせてしまったように、日本企業の希望退職もまた、誰を残すかではなく、誰が動けるかに組織の未来を委ねてしまっています。
制度の問題は退職金の額そのものではありません。
本当の問題は、会社が誰に残ってほしいのかを考えないまま制度を動かしてしまうことなのではないでしょうか?